Ⅱ−1−1
近年の激甚化・頻発化する自然災害に対応するため,立地適正化計画においては,災害の危険性の高いエリア(災害ハザードエリア)に居住誘導区域を定めないこととされ,特定都市河川浸水被害対策法の改正では,新たに災害ハザードエリアを指定する制度が設けられた。これらの災害ハザードエリアのうち,住宅等の建築や開発行為等が規制される区域名を複数挙げ,そのうち2つの区域について,区域の概要と規制の内容を説明せよ。
・災害ハザードエリア
・区域名の内容と規制の概要
Ⅱ−1−2
街路事業について,新規事業採択時評価として行うB/C(費用便益比)の算定方法を,計上する便益(十分な精度で計測できる金銭表現可能な基本3便益)を明らかにして,述べよ。また,基本3便益以外のストック効果を複数挙げよ。
Ⅱ−1−3
市街地における道路は,建築物との関係において,単に通行の場であるのみならず,建築物の利用,災害時の避難路,消防活動の場,建築物等の日照,採光,通風等の確保など安全で良好な環境の市街地を形成するうえで極めて重要な機能を果たしている。
こうした道路の機能が発揮できるよう,建築基準法に定められている,周辺の道路の状況によって建築物やその敷地に課せられる規制を2種類挙げ,それぞれの特徴を説明せよ。
Ⅱ−1−4
都市の農地については,平成3年の生産緑地法改正による生産緑地制度のもと平成4年に三大都市圏で一斉に生産緑地地区が指定され,平成29年の法改正で,特定生産緑地制度が設けられた。平成3年の法改正による生産緑地制度の概要を説明したうえで,特定生産緑地制度を必要とした背景及び制度の概要について説明せよ。

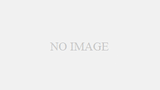
コメント