| 立体換地とは、 | 土地区画整理法第93条に基づく制度従前の土地の権利について換地を定めずに、建物及び敷地の権利を与えることができる制度。 | |
| 法に基づく立体換地のパターン | 過小宅地型 | 公共団体等の施工者が、過小宅地に対して立体換地を実施 |
| 高度地区型 | 公共団体等の施工者が、防火地域及び高度地区が定められた区域において立体換地を実施 | |
| 申出・同意型 | 施行地区内の所有者等の申し出、同意のあった宅地を立体換地。ずべての施工者が実施可能 | |
| 特徴 | 市街地再開発事業と比較して、法制度上の制約が少ない①より簡易な手続きでスピード感を持って実施可能 ・高度利用地区など事前の都市計画決定が不要 ・組合施工等においては、事業の都市計画決定が不要また、土地区画整理事業と市街地性開発事業等を併用した場合に比較して、同一事業(土地区画整理事業)の中で行うため、手続きや事業を円滑に進められる。②地権者に対して、よりニーズに柔軟に、より負担なく、実施可能 ・土地⇒土地 土地⇒建物(立体換地)を選択できる。⇒柔軟また、土地区画整理事業のみの場合(建築は自立再建)に比較して ・施工者側で、建築物の計画⇒整備⇒登記をすべて行うため、権利者の自立再建の負担が軽減できる。⇒負担少 ・立体換地建築物取得に係る税控除が受けられる。③零細権利者の割合が高い地区での小規模共同化(共同建物)といった場面でも、事業成立が可能再開発事業では、取得床が狭小となり、再建が困難となる零細権利者でも、事業成立が可能 ・零細権利者でも一定の床面積の取得が可能また、土地区画整理事業のみ場合と比較して、 ・保守床の売却益で事業収支の成立性の向上が可能(立体にすれば狭い地上の土地よりも売れやすい?) ・特に、減価補償地区でも、立体換地床の価値分の減価買収の低減が可能(立地換地にすることによって、少し価値が上昇するので、その分の減価分が相殺?) ・通常の換地を受ける者も土地の減歩率の緩和を享受できる。(全体的な価値が上がることによってい減歩率も緩和) | |
立体換地制度とは?
 土地区画整理事業
土地区画整理事業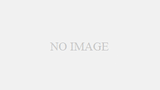
コメント